第1章:気づけば私、干物でした
起きたら13時過ぎ。天気はまあまあ、洗濯物は部屋干しのまま。冷蔵庫を開けたら、納豆とウーロンハイの缶が3本。昨日の記憶はあるけど、別に誰とも喋ってない。これが“私の日常”。
名前はルミ。27歳。昼は保育士、夜は競馬。休日は一歩も家を出ない、そんな干物女。
でも最近──
「……あの部屋、変なんだよね」
隣の部屋。
何がって、時間。深夜2時とか3時とかに物音がする。 しかも人の気配はあるのに、姿は見えない。配達物は一切なし、洗濯物も干されてない。
なのに、女の笑い声がすることがある。
夜中の静かな時間に、うっすら聞こえる「キャッ」ていう声。 それも、週に何度もだ。
正直、気味が悪い。でも、どこか気になる。
私はこの部屋から出たくない。でも、あの部屋のことだけは知りたい。
第2章:最初の接触
その日も、昼まで寝て、カップラーメン食べて、部屋で競馬の出走表を眺めてた。
ピンポーン。
「え、なに……出る服ない……」
インターホンの画面を見ると、黒いフードをかぶった男。顔は見えない。荷物も持ってない。
──誰?
居留守を決め込んだ。
でも、5分後。
カツ、カツ、カツ。
玄関の前をゆっくり歩く足音。 そのあとに、ポストが開閉する音。
怖くて、息を止めた。
やがて──カチ。
鍵の音がして、隣の部屋に入っていく気配。
「……あれ、隣の人?」
そう、気づいた。 あの黒フードは“隣の住人”だ。
私はその日、初めてカーテンの隙間から、隣のベランダをのぞいた。 何もなかった。誰もいない。 でも、気配だけが、ずっとそこにあった。
第3章:彼の正体
それから私は──干物女のくせに──隣人のことを毎日観察するようになった。
・朝出る様子はない ・ゴミ出しもしない ・宅配も受け取らない ・でも、夜になると、部屋の明かりがつく ・週に2〜3回、女の影が出入りする
彼は何者なのか?
ある日、私はポストを見に行った。 隣のポストには「三宅」という名前があった。
その夜、試しにX(旧Twitter)で「三宅+このマンション名」で検索してみた。
出てきたのは──
《キャバクラ嬢が言ってた“ヤバい男”ってこの人じゃない?》 《金払いはいいけど、絶対に名前を名乗らない》 《現金で10万ポンとくれるって聞いた》
震えた。まさか、本当に“ヤバい人”……?
でも、目が離せなかった。
第4章:つながる気配
ある夜、私の部屋に小さな封筒が入っていた。 差出人不明、中にはメモが一枚だけ。
《見てたでしょ?次は君の番だよ》
背筋が凍った。
──バレてた。
あの人に、私が見てることが。
その夜から、毎晩、隣のベランダから何かの気配がするようになった。 部屋の中なのに、誰かに背中を見られてるような感覚。
私はテレビをつけっぱなしにして寝るようになった。 電気も、消せなかった。
でも、怖いのに、やめられなかった。
見たい、知りたい、でも怖い。
気づけば私は──干物女じゃなく、観察者になっていた。
第5章:干物女の逆襲
ある夜、私はインターホン越しに言った。 「すみません、ポストに何か入ってたんですけど……」
しばらく沈黙があったあと、声が返ってきた。 「悪い。遊びすぎた。気にしないで」
淡々とした、感情のない声だった。
私は笑った。 「……じゃあ、次は私の番ですね」
その夜、私はベランダからそっとスマホを構えて、彼の部屋を撮った。
“観察される者”から、“観察する者”へ。
私の干物な日常は、少しだけ、色を変え始めていた。
第6章:仕掛けのある朝食
次の日、私のポストに小さな紙袋が入っていた。中にはドリップコーヒーと一枚のメモ。
《こっちからも、観察してた。少しはマシな味になったか?》
──まさか、コーヒーまで…?
警戒しつつも、私はそのコーヒーを淹れた。香りが良すぎて、正直ちょっと笑ってしまった。
「なにこれ、やるじゃん……」
この瞬間から、私の日常は、彼との“見えない手紙交換”に変わっていった。
第7章:ベランダ越しの通話
ある晩、私が部屋で酔っていたとき──ベランダ越しに低い声が聞こえた。
「お前さ、ずっと見てただろ」
「そっちもでしょ」
ベランダ越しに、私たちはスマホを使って通話を始めた。顔は見えない。 でも、声だけはやけにリアルだった。
「名前、教えてよ」
「……三宅」
「知ってたよ」
それから毎晩、私たちは声だけで会話するようになった。 干物女の部屋に、少しだけ温度が生まれた。
第8章:知らなきゃよかった過去
ある日、彼の部屋に警察らしき男たちが来た。 数分の会話。すぐに帰っていった。
気になって、私はまたXを検索した。 すると──
《あの三宅って男、昔詐欺グループの幹部だったらしい》 《今は足を洗ってるけど、裏では何してるかわからない》
一気に血の気が引いた。 でも私は、ベランダに出て、あえて言った。
「本当なの?」
彼は一言だけ言った。
「知らない方がよかった?」
第9章:選んだ日常
私は考えた。怖い。でも──楽しい。 こんなに人とつながったのは、いつぶりだろう?
日常なんて、とっくに壊れてた。 干物女だった私が、ここまで関わってしまった。
でもそれでも、私は思った。
「また、声が聞きたい」
ベランダ越しの関係でいい。 それでもいい。
私の干物な日常に、ちょっとした刺激と会話が生まれた。
それで、十分だった。
終章:干物女子、境界線を超える
ある夜、私は部屋の鍵を閉め忘れて寝てしまった。 目が覚めたとき、キッチンに1枚の紙が置いてあった。
《お前は、干物女のままでいろ。それが、俺の好きなとこ》
震える手で、その紙を握りしめた。 でも、私は笑っていた。
今日もまた、ベランダ越しに言う。
「三宅さん、今日は来るのかな」
それから、私は週末にまとめて「記録」を残すようになった。 彼の出入り、来客、服装、物音、会話の断片──
まるで、趣味のように。
彼が誰かなんて、もうどうでもよかった。 私にとって彼は、
“この干からびた生活にスリルを与えてくれる存在”
だったから。
私は今日も部屋でウーロンハイを飲みながら、そっとつぶやく。
「三宅さん、今日は来るのかな」
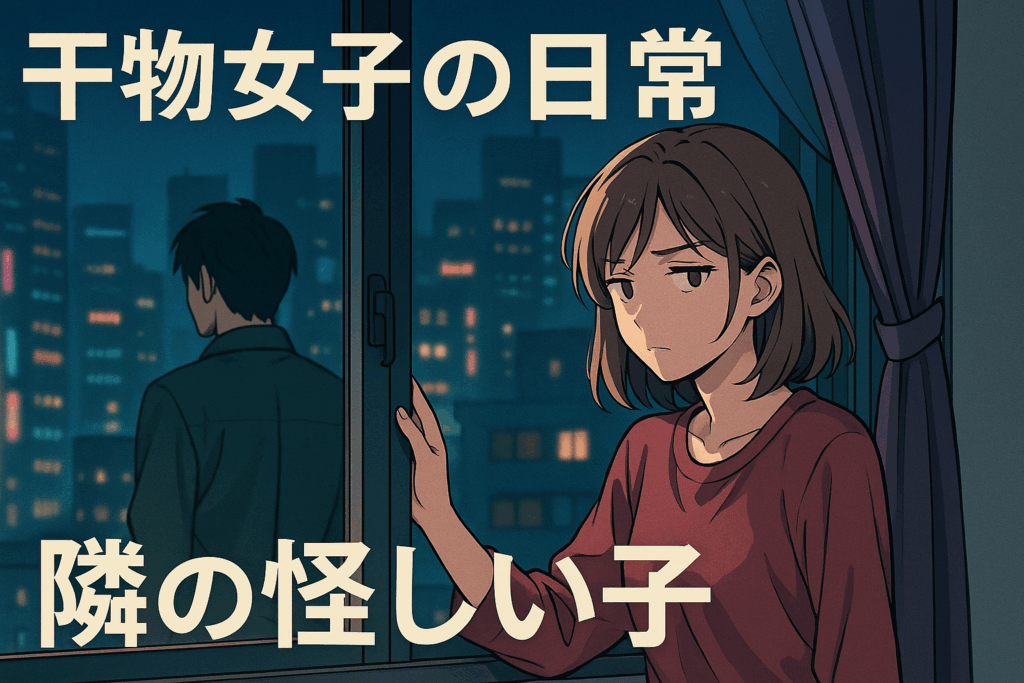



コメント