🍽 第1章:新宿の路地裏に、ヤバすぎる“神店”があると聞いて
「うまい・安い・早い・ヤバイ」
この言葉を地で行く飲食店が、新宿の路地裏に存在する──そんな噂を聞いたのは、SNSのとある匿名投稿がきっかけだった。
「マジで人生変わるレベル。都内最強のコスパ飯、行って損なし」
こう書かれていた投稿には、ボリューム満点の唐揚げ定食の写真が添えられていた。金色に輝く衣、溢れる肉汁。しかも、それがワンコイン以下で食べられるというのだから驚きだ。
半信半疑のまま、私はその店「からバカ食堂・新宿ゴールデン口店」へ足を運ぶことにした。
店名からしてヤバイ。が、期待も高まる。

新宿駅西口から徒歩7分。
居酒屋と風俗店が入り交じるごちゃごちゃした通りを抜けた先に、その店はあった。
正直、見た目はしょぼい。木の引き戸に「営業中」の札がかけられているだけ。看板には、漫画風のフォントで「からバカ」と描かれており、外観だけなら完全にスルーするレベルだ。
しかし、引き戸を開けると──
目に飛び込んできたのは、サラリーマンや若い女性グループで賑わう店内と、立ち上る揚げ油の香り。
「いらっしゃいませー!」
ホールを仕切るおばちゃんの声が店全体に響く。座席はカウンター8席、テーブル4つの小さな構成。狭いが、活気がある。そして何より驚いたのが、壁一面に貼られた“赤札”だ。
「バカ盛り唐揚げ定食 ¥490」
「味玉ラーメン+焼売定食 ¥580」
「昼割:ご飯おかわり自由・ドリンク無料」
……マジか。ここ、本当に都内だよな?
物価がバグっている。いや、空間そのものが昭和レトロすぎて、時間軸まで歪んでいるのかと思うほど。
「お姉さん、初めて? なら唐揚げ定食が鉄板よ!」
そう声をかけてくれたのは、厨房で鍋をふるっていた店主・鬼沢(きざわ)さん。見るからに頑固そうな風貌だが、声には不思議な優しさがあった。
「うちは“唐揚げバカ”の略で“からバカ”。とことん唐揚げに命かけてんの。油もブレンド、衣も毎日配合変える。うまくなかったら金返すよ」
言い切った。
この一言で、私は確信した。
この店──当たりだ。
注文してから、わずか6分。
目の前に現れたのは、圧倒的なボリュームの唐揚げ定食だった。
直径10センチ級の唐揚げがゴロゴロと5個、山のように盛られている。脇には千切りキャベツ、山盛りごはん、味噌汁、そして小鉢に自家製のぬか漬け。これで本当に490円? と目を疑った。
一口目を頬張った瞬間、私は「やられた」と思った。
外はカリッ、噛めば中から肉汁があふれ、鶏もも肉がまるで蒸し鶏のように柔らかい。下味がしっかり染みていて、ご飯が止まらない。
「……なにこれ、ファーストクラス?」
つい口にしてしまうほど、味の完成度が高い。
聞けば、肉は都内の専門業者から朝どれの国産若鶏を仕入れ、塩水に一晩つけたあと、オリジナルブレンドの香味油で二度揚げしているという。
さらに驚くのは、このレベルの料理が常に同価格・定休日なし・昼夜問わず提供されていることだ。
「うちは腹減らしてるヤツの味方なんだよ。こっちが勝手に安くしてるだけさ」
と笑う鬼沢店主。
……惚れてまうやろ。
こうして、私は“コスパ最強グルメ”という言葉の本質を見た気がした。
それは、単なる価格の安さではない。
**「うまさと、心意気」**がそこにはあったのだ。
第2章:それは「愛情の味」だった──ルミ、箸が止まらない夜
「これは……ダメ。おいしすぎて、脳がバグる」
ルミは両手で箸を握りしめたまま、しばし固まった。
その日、彼女が注文したのは店主いち押しの「味噌ダレ豚ステーキ定食」。
鉄板に乗ったジューシーな豚肩ロースが、ジュワァ…と音を立てながら運ばれてくる。
目の前で立ちのぼる湯気、甘辛い味噌ダレの香ばしさ。
「胃袋を刺激する匂いだけで、ご飯が3杯いける」そう感じさせる一皿だった。
第一口、噛んだ瞬間、ルミの中に何かが弾けた。
「えっ……なにこれ、どこかで食べた記憶が……あれ、泣きそう……」
かつて、ルミが小学生の頃。
保育園で仕事を終えた母が、夜遅くまで頑張って作ってくれた豚の味噌焼き弁当。
それに限りなく近い、あの“家庭の味”だった。
「誰かのために作られた料理って、やっぱり違う……」
どこか懐かしく、でも圧倒的に“今”の旨味がある。
添えられた小鉢には、甘く炊いた切り干し大根。
味噌汁の具には旬のナスと豆腐。
すべてに「余計なことはしないけれど、ちゃんと手をかけている」という美学があった。
この瞬間、ルミの心は完全に掴まれた。

「胃袋が恋するって、こういうことかも」
思わずそんな言葉を呟きながら、彼女はスマホを手に取った。
「この感動を、誰かに伝えたい……」
💡ここでルミのおすすめグッズ!
「食後の脂肪吸収、ちょっと気になる…」というあなたに!
▶️【ルミおすすめ】脂肪ブロック系サプリ
▶️【食べ過ぎリセット】夜に効く!燃焼サポートドリンク
その夜、ルミはしっかりデザートまで平らげ、笑顔で言った。
「このお店、推すしかないね。推しグルメ、登録っと!」
「でも…ほんとに、食べ過ぎ注意だな、これ」
ルミは少し頬を紅潮させ、スマホのカメラを静かに構えた。
料理だけではない。
この店の魅力は“空気”そのものにあった。
木の温もりを感じるテーブル、壁に飾られたレトロなポスター、耳に心地よいBGM――
昭和の懐かしさと、今風のセンスが絶妙に融合した空間。
「こういうとこ、男の人って知らないでしょ?」
そう言いながら、ルミはInstagramに#隠れ家ごはん #豚ステーキ #飯テロ注意 を添えて投稿。
彼女にとって、“食”は単なる満腹手段ではなく、自分を整える時間だった。
と、そこへ店員が静かに近づく。
「サービスのデザートです、女性のお客様だけに…」
小皿に乗った手作りプリンがそっと差し出された。
「えっ……なにこのお得感。こんなの…好きになっちゃうじゃん」
その優しさに、ルミは思わず頷いた。
まるでこの店が「お疲れさま」と言ってくれているような気がして。
「たぶん私、また来るね。いや、絶対来る」
その夜、ルミの心には“忘れられない店”が刻み込まれた――。
第3章:記憶に焼きつく、”また来たい”の魔法
「ひと口で、なにかがほどける感じだったんだよね……」
帰り道、ルミは独り言のようにそうつぶやいた。
唐揚げも豚ステーキも完食したのに、身体は軽く、心だけが満たされている。
“うまい・安い・早い・ヤバイ”――
この店を説明するには、あのキャッチフレーズ以上の言葉が必要だった。
ルミは改札を抜ける直前に立ち止まり、ふとスマホを開いた。
投稿したばかりの料理写真には、すでに「いいね」が100件近くついている。
「ねえ、どここれ!?」「安すぎて逆に怖い」「行きたい、今すぐ!」
コメントの嵐。
だけどルミは、少しだけ言葉を濁して答えることにした。
《場所は…秘密。でも、女ひとりでも安心して入れるよ。最高の“ヤバイ店”だから。》
それは、誰かに自慢したいけど、あまり知られたくない。
そんな“宝物”を手に入れたときの複雑な感情だった。
その店には、「完璧な接客」も「高級な内装」もない。
けれど、そこにあるのは、誰かの「生き方」だった。
たとえば、唐揚げの皮ひとつにも無駄な油がないこと。
味噌汁のわかめがやけに新鮮だったこと。
水を持ってくるタイミングが、まるでルミの呼吸と合っていたこと。
ひとつひとつが、ルミの心をじわじわと溶かしていった。
📱 ルミ愛用の食べ過ぎ防止の秘密兵器
どんな店も、どんな味も、しっかり記録して、でも食べ過ぎ防止!
おいしい瞬間を逃さず残して、次のグルメ探訪にも大活躍!
ルミはポケットから、ボロボロの手帳を取り出した。
高校時代から愛用しているその手帳には、これまで訪れた飲食店がびっしりと記されていた。
彼女は小さな文字で、今日の店の名前を書き込み、
その横に――
「◎リピ確定、最高に優しい味。鬼沢店主、ありがとう。」
と、赤ペンで書き足した。
ルミにとって、「食」とは単なるグルメではなかった。
心がすさんだ日も、嬉しいことがあった日も、食があれば前に進めた。
「誰かと一緒に食べたい」と思ったとき、
それはその人を“自分の人生に招待したい”という意味だった。
だからこの夜、ルミは決めた。
「ナジカにも、あの唐揚げ食べさせたいな…」
美味しいものを分かち合いたい人がいる。
その気持ちこそが、彼女にとっての“幸せの指標”だった。
第4章:ナジカとルミ、個室で交わすグルメ作戦会議
「で? あんたがそんな顔して呼び出すなんて、どんなヤバイ店だったのよ?」
個室居酒屋「こだま」の一番奥。
掘りごたつ式のテーブル席で、ナジカが腕を組みながらグラスを傾けた。
スレンダーな身体に張りのある胸、すっきりした輪郭に鋭くも美しい目元。
その姉御肌の雰囲気とは裏腹に、声にはどこか包容力があり、居心地がいい。
「うん……ナジカさんにも絶対食べてほしいって、思っちゃった」
ルミが差し出したのは、スマホの写真フォルダ。
ジューシーな唐揚げ、ボリューム満点の豚ステーキ、彩りのいい小鉢たち。
どれも安価とは思えない品揃えだった。
「これで一人980円?」
「そう。ドリンクつけても1500円いかないの。信じられる?」
ナジカは鼻で笑った。
「信じたくないわよ。あたしたちがどれだけグルメに金つぎ込んできたか。
食い物は高くてうまいか、安くて不味いかのどっちかが定番でしょ?」
「ところがさ、これは…例外なの。すごく、あったかくて…ね」
ルミがその日の思い出をぽつりぽつりと語りだす。
ナジカは最初、笑って聞いていたが、次第に表情が変わっていく。
「……なるほど。オーナーが元職人で、下町育ちで、女性客の比率が高い、と。
調理と接客、どっちも一人でこなしてるのか。やるわね」
ナジカの脳内には、もう地図とデータが組み上がっていた。
「……その店、名前、何?」
「“味福亭(みふくてい)”っていうの」
「場所は?」
「それは、まだ秘密。紹介制ってことで……ね?」
ルミの悪戯っぽい微笑に、ナジカも思わず笑った。
🍽【プロの舌も唸らせる!自宅で楽しむ高コスパグルメ】
「味のプロが選ぶ!本気で美味いお取り寄せセット」
🛒今だけ限定価格 ⇩
「じゃあさ、その店……今後どうするつもり?」
「広めたい。けど、壊したくない」
ルミのその言葉に、ナジカはグラスを置いて前のめりになる。
「だったらあたしが協力してやるわよ。
紹介制のグルメサイト、あたしたちで立ち上げようか。
“ヤバログ”みたいな名前で、選び抜いた“ほんとうに勧めたい店”だけを載せるの」
「え? あたしたちが、グルメ選抜チームになるってこと?」
「その通り。SNSでも、動画でも、写真でも紹介して。
アフィリエイトも組んで、ちょっとでも利益出せるようにしてさ」
「え、ちょっと待って。もしかしてそれ、ビジネス……?」
「当然でしょ。せっかく才能と味覚あるんだから、使わなきゃ損よ。
ルミ、あんたさ、意外と人を見る目あるんだから」
ナジカのその言葉に、ルミは一瞬黙った。
でも、心のどこかがじんわりと熱くなるのを感じた。
ルミとナジカ、2人の個室居酒屋でのグルメ会議は、
単なる「うまい店」から始まったはずが、いつの間にか「新しい物語」になっていた。
次の店を探しに行こう。
もっと、誰かを笑顔にできるように。
そして、あの“味福亭”のような、静かに沁みる名店を――
第5章:ナジカの眼(まなこ)と裏の勘 〜「味福亭」の奥に潜む匂い〜
「この店……やっぱり、只者じゃないわね」
ナジカは、静かに箸を置いた。
目の前の唐揚げは絶品だった。外はカリッと香ばしく、中はジューシーで柔らかい。
ルミが言っていた通り、確かに“うまい・安い・早い”の三拍子が揃っている。
けれど、ナジカの本能が告げていた。
この店には、もう一つ“何か”がある――と。
「いらっしゃい」
奥から現れたのは、鬼沢という名の店主。
割烹着姿、細身、無口。目が合うと、静かな笑みを浮かべるが、
その笑顔が“作られている”ことに、ナジカはすぐに気づいた。
《この男、ただの料理人じゃない》
そう確信できたのは、声の抑揚と指先の動きだった。
元夫が“裏の世界”にいたナジカにとって、そういう“勘”は鋭い。
料理の盛り付けひとつにまで染み出す“職業的な緊張感”。
長年、何かに追われるように、誰かを見つめるように、生きてきた人間の仕草だった。
「ルミ、あんたさ、この店の情報どこまで掴んでる?」
「えっ?……近くの保護者が“隠れた名店だ”って。紹介制って聞いたのもそこから」
「ふーん」
ナジカは、ふと厨房の奥に目をやった。
棚の下、少しだけ開いた引き戸の奥に、古い木箱が見えた。
“味福亭”という名に似つかわしくない、無骨な黒い箱。
それは、かつてナジカがいた裏社会で“取引品”を入れていた木製トランクと酷似していた。
(まさか、とは思うけど……)
ナジカは、あえて何も言わず、静かに会計を済ませた。
だが、その瞬間、鬼沢がふと彼女を見た――その目には、一瞬の「警戒心」が浮かんでいた。
《気づいたことに気づかれた》
それが、ナジカの中に火をつけた。
🧳【プロの女探偵も推薦⁉】 ⇩
ナジカの推測、本物の勘
「ナジカさん……どうしたの?」
居酒屋を出て歩き始めたルミが、不安そうに訊く。
「ルミ、ちょっと本気で言うけど、この店……“美味しい”だけで終わらせたらもったいないわよ」
「え?」
「たぶん、だけど――この店、過去を背負ってる。
料理と接客だけじゃない、もっと深い“物語”があるの。
あたしが動いてた世界と、少しだけ匂いが似てる」
ルミは少し戸惑っていたが、ナジカの言葉に、静かに頷いた。
「じゃあ……調べてみる?」
「ええ。次は、あたしの番ね。
“味福亭”が、なぜこの立地でこの価格で、そしてこの味で勝負できてるのか――
その裏に何があるのか、あたしの勘が知りたがってる」
ナジカは、スラリと脚を前に出しながら笑った。
「次は、単なる“グルメ記事”じゃなくて――
“ルポ”として書くわよ。覚悟しときなさい、ルミ」
ルミは、一瞬驚いたような顔をしたあと、笑った。
「じゃあ……私も“編集”として、付き合いますね」
味だけじゃない。
価格だけでもない。
その奥にある“何か”が、今、2人の前に扉を開こうとしていた。
ナジカの眼差しの先にあるのは、
「コスパ最強グルメ」という言葉だけでは語りきれない、
ある一人の“料理人の過去”と、2人の“女たちの物語”。
ナジカはスマホを取り出し、何気ないフリで“味福亭”の外観を数枚撮影した。
そのアングルには、防犯カメラの設置位置や、裏手への細い通路までがしっかりと収められていた。
「……最近、こういう隠れ家っぽい飲食店、やたら増えてるけどさ」
「SNS映えとか、雰囲気重視とかって言うよね?」とルミが返す。
「違うわ。あれは“逃げ道”の構造。
出入りのしやすさ、カメラ死角、開店時間の不規則性――全部が“普通じゃない”のよ」
ナジカの視線は、ただの店舗の裏口を、まるでかつての“アジト”を見るかのように射抜いていた。
彼女の中で眠っていた感覚が、静かに再起動しはじめていた。
表の顔と裏の匂い――そのどちらにも敏感なナジカだからこそ、この物語を“グルメレポート”として終わらせるつもりはなかった。
「この街には、まだ“物語”が埋もれてる。掘り起こす価値があるわ」
ルミが、静かに相槌を打った。
2人はまた、“食”を超えた真実の探求へと、歩き出すのだった。
第6章:鬼沢の正体
その晩、ナジカはルミと別れたあと、繁華街をひとり歩いていた。
ネオンが滲む夜の街。どこか浮かれた空気の中、彼女の目は一層鋭さを増していた。
「鬼沢……まさかまだ、この界隈にいたなんてね」
鬼沢――かつてナジカの夫だった男。
裏家業に生き、金と力にしか興味のなかった男。
10年前に姿を消し、死んだとも噂されていたが……この“味福亭”の動きで、彼の息がかかっていることをナジカは確信した。
翌日。ナジカは手慣れた手つきで、古いコネクションに連絡を取っていた。
「アタシだよ。例の“東京北”の件、鬼沢って名前で照会して。あと、最近の出入り業者、金融系、裏口契約も全部洗って」
しばらくして届いたデータに、ナジカは眉をひそめた。
そこには鬼沢の“新しい顔”があった。
【鬼沢 勝己(改名:大野 克巳)】
表向きは「再生医療企業」の経営者、しかし裏では半グレ集団の資金洗浄拠点の運営者。
彼の企業は、「睡眠改善」「メンタルヘルス」「若返り」といった健康系ジャンルで広告を展開し、
大量のアフィリエイト案件に資金を流し込み、表向きの顔を隠していた。
「ぐっすり快眠!話題のCBDサプリメント」
✔ ストレスで眠れない?
✔ 寝つき改善とメンタルサポートに。 ⇩
「……あいつ、まさか“合法”に寄せてきてるとはね」
ナジカは舌打ちした。
これはただの“飲食店の潜入”では終わらない。
もっと大きな金の流れと、古い因縁が絡んでいた。
ルミから届いたメッセージが鳴る。
「ナジカさん、例の店だけど、今日また新メニューが出るみたいよ。行く?」
「了解。ついでに鬼沢の“餌場”がどれだけ広がってるか、確かめに行くか」
ナジカは、手早く荷物をまとめ、黒いトートバッグに忍ばせた。
「盗聴防止×持ち運びスマート」
✔ 電波遮断 電波カットケース
✔ スマートキー スキミング防止 ⇩
裏の仕事では、いつでも“想定外”を想定しておかなければならない。
鬼沢は、ナジカにとって“片をつけなければならない過去”だった。
それは、ルミがまだ知らないナジカの“闇の履歴書”。
二人がまた居酒屋の個室で出会ったその夜、鬼沢の使いと思われる男がカウンターに座っていた。
スーツのボタンを開け、タバコをふかしながら、時折こちらに目をやっていた。
ルミが言う。
「ナジカさん、あの男……目が笑ってない。ヤバい気がする」
「大丈夫。こっちは10年もこういう連中と仕事してきた」
そして、ナジカはそっとルミに耳打ちした。
「この後、あなたはこのバッグを持って先に出て。私は……尾行を撒く」
ルミは息を呑んだが、うなずいた。
そう、彼女もただの“グルメレポーター”ではなくなっていた。
味と人と真実――
この“街の底”には、まだ誰も見たことのない物語が転がっている。
ナジカの目に、かすかに懐かしい怒りと決意が宿っていた。
鬼沢をこのまま逃がすわけにはいかない。
「探偵も使う小型録音デバイス」ボイスレコーダー 長時間連続録音 録音機 超小型 ICレコーダー
✔ 重要な会話をクリア録音
✔ 音声感知で自動起動 ⇩
第7章:ルミの過去
鬼沢の正体と、ナジカの過去がついに交差し始める。
そして、ルミの“意外な行動”が、全てを加速させることに…。
夜風が冷たい。
ルミは一人、帰宅の道を急いでいた。
ナジカから預かったバッグの中に、何が入っているのかを確認する勇気はなかった。
ただ、彼女の胸には妙な緊張感と、どこか懐かしい“震え”があった。
「……また、こんな世界に戻るなんてね」
彼女は昔の自分を思い出していた。
大学時代、恋人だった男は、関東某所の“情報屋”として裏稼業を営んでいた。
初めは「ただのスリル」だった。
だが、ルミは徐々にその世界の“怖さ”と“冷たさ”を知っていった。
裏切り、恐喝、監視。
そして、“録音”
「ナジカさんの目……あの頃、アイツの目と似てた」
そうつぶやいたとき、ルミのスマホが震えた。
──番号非通知。
画面を見た瞬間、心拍数が跳ね上がる。
通話ボタンを押すと、低い男の声が耳に飛び込んできた。
「久しぶりだな。もう“あのときの件”は忘れたのか?」
「……鬼沢?」
沈黙。
「オレは“彼”のことなんか知らない。だが、ルミ、お前が“ナジカ”と組んでるのは分かってる」
「……何が言いたいの?」
「お前は、あのバッグの中身を見ていないようだな。ナジカに騙されているぞ。お前も“捨て駒”になるつもりか?」
通話はそこで切れた。
ルミは立ち尽くした。
心臓がバクバクと鳴っている。
ナジカは信用できるのか? それとも…。
バッグのジッパーに手をかける。
開けた中には──1冊の黒い手帳と、レコーダー、そしてUSBメモリが入っていた。
「……これ、証拠?」
手帳にはびっしりと取引記録や関係者リスト、資金の流れが記されていた。
しかもその中には、数年前に自分が関わった“あの事件”の名前までが…。
「嘘……この手帳、私を巻き込むつもりで──?」
ルミの手が震えた。
だが、次の瞬間にはスマホを開き、検索していた。
“自宅でできる盗聴器・GPSの発見方法”
“自衛用の電波遮断グッズ”
自分が“誰かの道具”にされるのはもう嫌だった。
彼女の中の“戦う自分”が再び目を覚ました。
「鬼沢……あんたがまだこの街で何かを動かしてるなら、私は止める。私も、過去から決着をつける」
次の日。
ルミはナジカの元へ向かった。
「ナジカさん、話がある。あのバッグのこと」
ナジカは煙草に火をつけながら、黙って頷いた。
「……全部読んだのね」
「読んだ。あんたの過去も、鬼沢のことも。だけど、私にも“片づけたいこと”がある」
二人の目が重なる。
かつては表と裏。
強さと弱さ。
知と情──まったく違う世界を歩んできた二人が、今、同じ敵に向かおうとしていた。
その夜、ルミは街に溶け込むように、調査を再開した。
味福亭の裏口、怪しい男たちの出入り。
そして、ある中年男の顔──
それは、鬼沢が最も信頼していた“左腕”だった。
「ついに出てきたわね。…次で終わらせる」
【女性専用セルフディフェンスグッズ】
✔ 軽量防犯アラーム+緊急通報ボタン
✔ 鞄に常備できるお守りセット ⇩
第8章:鬼沢との対決(ルミとナジカの逆襲)
鬼沢との直接対決がついに始まる──
ナジカとルミ、そして“過去の罪”が交錯する中、誰が真実を握るのか。
闇と光が交錯する、女たちの逆襲が始まる。
深夜2時過ぎ。
個室居酒屋「隠密庵」の裏口で、黒ずくめの男たちが動き始めていた。
その中には──鬼沢の姿があった。
「……今夜、最後の受け渡しだ。ナジカが動いたようだな」
その声を、ある人物が屋上から無音カメラで捉えていた。
ルミだった。
「映像、ナジカさんに送るね」
彼女の指は震えていない。
かつて恐怖に震えていた女は、もうそこにはいなかった。
ナジカのスマホに、鬼沢の顔と声が届く。
「……決まりだね」
ナジカは、バー「UTAGE」の奥の個室にいた。
居合わせたのは、警察の非公式チーム。
彼らは裏社会の動きを知りつつ、ナジカと過去に因縁を持つ“協力者”だった。
「もう逃げられない。証拠もある。今夜、終わらせる」
数時間後──
鬼沢はいつものように「味福亭」の“閉店後の裏の間”に入った。
が、そこにはルミとナジカ、そして複数の警官が待っていた。
「ようこそ、鬼沢さん。ラストオーダーですよ」
ルミの声は静かだった。
「貴様……!」
鬼沢は拳を握ったが、周囲に取り囲む私服刑事の数に、観念した。
「これは、あのときの……報いか」
「ええ、そしてこれは、“今”の私たちの選択です」
ナジカがそう言い終える前に、手錠の音が響いた。
そして──
事件が解決した数日後、ナジカとルミは再び個室居酒屋「隠密庵」のテーブルにいた。
今回は、本当にただの“飯会”だった。
「ねえ、ナジカさん」
「ん?」
「やっぱりこの店……“うまい・安い・早い・ヤバイ”の全部詰まってるね」
ルミが笑う。
「でも、ヤバイの意味が、前とは違うかも。
なんか、心の底から『生きててよかった』って味がする」
「……あたしも同じ気分だよ。胃袋に染みるな、この唐揚げ」
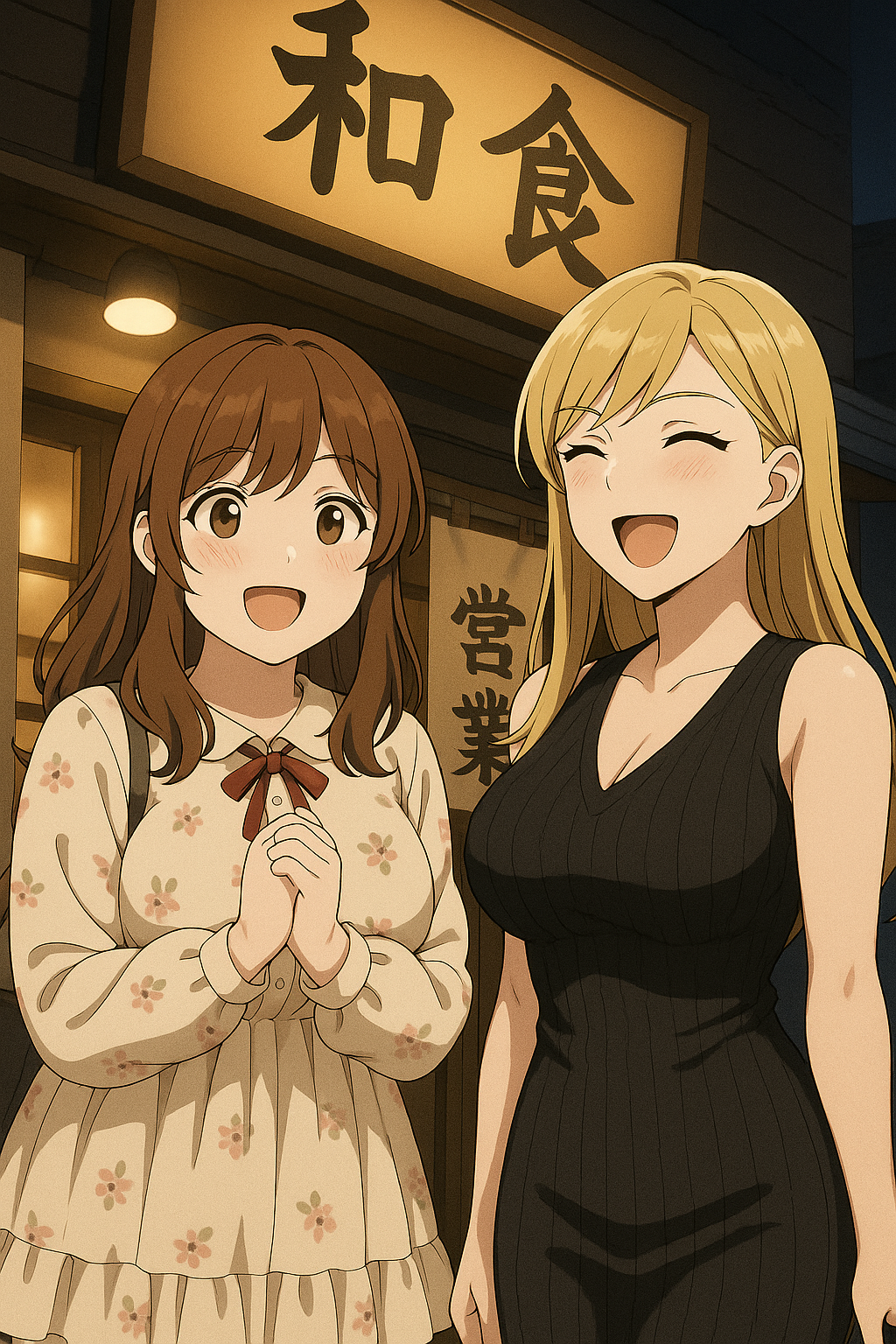
「また、来よう。今度は作戦抜きで」
「もちろん。……ていうか、毎週通うかも」
こうして、二人は“過去”を手放し、“日常”を取り戻した。
そして、今日も「隠密庵」の暖簾は揺れている。
第9章:常連たちの証言──“あの味”が忘れられない理由
「正直、もう他の店じゃ満足できないんスよね」
そう語るのは、会社員の佐藤氏(34歳・都内勤務)。
仕事終わりに必ず立ち寄るという「隠密庵(おんみつあん)」は、いまや彼の“帰る場所”になっていた。
「どのメニューもコスパ最高。特に『やみつき唐揚げ定食』は…一口で世界が変わる。これマジ」

🍚 主婦の間でも話題騒然!家族連れの証言
「子どもが“お代わり”って言ったの、この店が初めてでした」
と語るのは、品川在住の主婦・坂本さん。
平日は自炊派の彼女も、週末は「隠密庵」での外食を楽しみにしているという。
「特製の味噌カツ丼がね、肉厚なのに柔らかい!家庭じゃ再現できないから、いつも持ち帰りしてます(笑)」
✔ 電子レンジで簡単再現
✔ 肉なしでも“旨い”と噂 ⇩カクキュー 味噌カツのたれ 320g 3個
👨🍳 食通ブロガーも唸った!“最強の裏メニュー”
さらに注目すべきは、**“裏メニュー”**の存在。
取材班がこっそり情報を集めたところ──
「週替わりで変わる裏メニューは、公式には出してない。でも、店員さんに聞くと“知ってる人だけ”には教えてくれる。そこにこの店の“ヤバさ”が詰まってるんです」
と話すのは、人気食通ブロガーの“くいだおれ二郎”氏。
彼が絶賛していたのは、【焦がし醤油の炙りチャーシュー丼】。
「一口食べた瞬間、五感すべてが満たされました。あの体験は、まさに“食の悟り”ですよ」
📢 店外でも“隠密庵”ファンは増殖中!
SNSでも話題に事欠かない。
「#隠密庵」「#ヤバイ定食」「#胃袋つかまれた」のタグで毎日数十件以上の投稿が確認されている。
特に若者の間では、「TikTokでバズったあの店」として知られており、開店前から並ぶ日も珍しくない。
まとめ:この“口コミ力”が証明すること
味・量・価格だけでなく、**「記憶に残る」**こと──
それが、この店が“ヤバイ”と評される最大の理由なのかもしれない。
そして、常連たちは口をそろえてこう語る。
「もう、ここしか勝たん」
第10章:再訪──“あの味”と、もう一度
ルミが再び「隠密庵」の暖簾をくぐったのは、あの日からちょうど一週間後のことだった。
──目当ては、あの「罪深き味噌カツ丼」。
店内に入ると、香ばしい揚げ油と甘辛い味噌だれの香りが鼻腔をくすぐる。
ふと横を見ると、ナジカの姿があった。白いシャツに黒のロングスカート、相変わらずの“姉御肌オーラ”全開だ。
「お前も来たのかよ」
「…あんたも、でしょ」
どこか照れくさそうに笑い合う二人。だが、その目は本気だった。
🍽 最後の晩餐? それとも次なる戦略会議?
二人が頼んだのは、例の裏メニュー【焦がし醤油の炙りチャーシュー丼】と、伝説の【味噌カツ丼】。
「これさ……家で再現できたら、毎日でも食べるわ」
ルミがそうつぶやくと、ナジカがスマホを操作して何かを見せてきた。
「お取り寄せあるっぽいぞ。しかも“店舗監修”だってよ」
矢場とん 大満足セット ⇩
🧾 食後の“満足”と“宿題”
「ナジカ、また来ようぜ」
「そうだな。てか、次は別店舗の潜入調査もアリかもな」
ルミの瞳には、もう“ルポライターの光”が戻っていた。
元夫の影に悩まされていたナジカにも、久しぶりに“普通の女の顔”が戻っていた。
やはり、“うまい飯”には心をほどく力がある。
🚶♀️ そして、夜道をふたりで
「隠密庵」の灯りが遠ざかる。
静かな夜の街に響く、ルミのヒールの音と、ナジカのブーツの足音。
「なぁ、次はどんな“ヤバイ店”探そうか」
「……それは、お前の胃袋次第じゃね?」
笑い合いながら去っていく二人の背中。
その姿が、なんとも“うまくて、安くて、早くて、ヤバイ”──
最高の余韻を残していた。
🎁 まとめ:あなたも“隠密庵”の味を、自宅で。
この記事を読んで「行ってみたい」「食べてみたい」と思った方へ──
📝 ライターより最後に
あなたの街にも、きっとある“まだ知らない名店”。
その扉を開けるのは、この記事を読んだ“今この瞬間のあなた”かもしれません。
「うまい・安い・早い・ヤバイ!」
そんなグルメ旅、次回の探訪もどうぞお楽しみに。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af19614.a2dd7d00.4af19615.761a20b3/?me_id=1369455&item_id=10000100&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fduen1102%2Fcabinet%2F08563445%2F08996261%2Fimgrc0129690241.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af19aac.a81116ee.4af19aad.6c085bf2/?me_id=1360884&item_id=10000033&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fclasico2017%2Fcabinet%2F10608552%2F10771500%2Fblf3_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af0a063.e68a0b02.4af0a064.06e97287/?me_id=1213310&item_id=13467278&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3113%2F9784167773113.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1a303.c7c914f0.4af1a304.6e3c7fe3/?me_id=1434354&item_id=10000077&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakuten-mart-ichiba%2Fcabinet%2F11814032%2F11825870%2F67_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ab8bf47.6061fac3.4ab8bf48.e9834122/?me_id=1278256&item_id=22990202&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frakutenkobo-ebooks%2Fcabinet%2F1146%2F2000014161146.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1ad41.60f3b24c.4af1ad42.71acb022/?me_id=1362544&item_id=10001534&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ftaisho-directshop%2Fcabinet%2Ftmb%2Fcbd_top.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1b174.d32e2260.4af1b175.394c1dda/?me_id=1415326&item_id=10003808&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffujifujistore%2Fcabinet%2Fcsv-fuji-3%2Fleo-10007-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1b6d1.149c0962.4af1b6d2.9b9560ff/?me_id=1258833&item_id=10157954&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsafety-security%2Fcabinet%2Fimg1%2Fcamcam%2Fic004_th.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1bc4e.234544f7.4af1bc4f.3106d53a/?me_id=1313202&item_id=10013408&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fauc-prendre%2Fcabinet%2Fimg20%2Fpr-dbb-03-w.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1be9a.1fb1e40d.4af1be9b.cc581433/?me_id=1423475&item_id=10000146&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flifeso-store%2Fcabinet%2Fp%2Fbjq3-2.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1c1d6.cf4db56e.4af1c1d7.4cb489f2/?me_id=1369054&item_id=10002265&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbbq-wonderland%2Fcabinet%2Fempo%2F10443352%2Fera_tori_s_01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1c6cc.ef604d13.4af1c6cd.e569a5d7/?me_id=1394793&item_id=10004097&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fkeyroom-hida%2Fcabinet%2F2024-05%2Fis-key-11704-3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4af1ca0e.4b68f110.4af1ca0f.aea7125d/?me_id=1396415&item_id=10001623&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-food%2Fcabinet%2Fyabaton%2Fitem_mset_img01.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
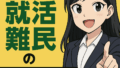

コメント